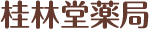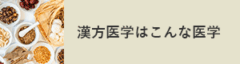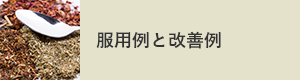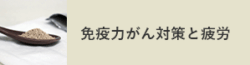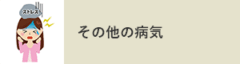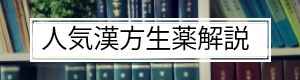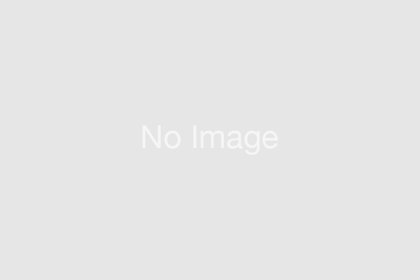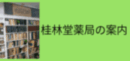東京都の漢方薬局・中目黒 桂林堂∣(中医学)は便利
東京都の漢方薬局・中目黒 桂林堂∣(中医学)は便利
中医学利用意味
東京都の漢方薬局の多くは漢方理論中医学を利用して漢方薬局、又は漢方専門店を運営して漢方処方等をお客様にお出ししています
このため漢方理論の中医学は漢方を作る時に処方選びに助けでくれます
中医学が無いと漢方薬局は運営でき難くなります
東京都は日本の首都で高尾から海岸の港区迄細長い形になっています
東京都には漢方薬局がかなりあり、西に八王子から湾岸迄かなりの漢方薬局があります
その中で目黒区にある中目黒駅2分の場所にある桂林堂薬局は、その東京都の少し東寄りに位置しています
東京都の漢方薬局・目黒区 桂林堂はなんだかんだ漢方歴と、お客様に漢方を作るのに便利な中医学をこの東京で利用してきました
東京で40年近く漢方の処方選びをするときに中医学が無いと漢方処方選びは難しくなります
便利な中医学があると、お客様に漢方処方を選ぶときに中医学を利用して見事に選ぶことができ、中医学は、漢方薬局にとって絶対な漢方理論になります
桂林堂薬局の、永山は、東京都八王子の大学卒業後相模原にある漢方薬局で中医学を学び初めてから漢方薬局へ勤めてから漢方薬局の経営と、便利な中医学を東京で40近く利用した経験があり、今では中医学が無ければ東京都で漢方薬局を運営することが出来ません
東京都八王子の大学卒業後に薬剤師 取得後から40年近い漢方 経験は、漢方専門の薬剤師としての自信がついたおかげか、お客様にある程度適切な漢方薬をお出しすることが出来るようになりました
その中で、お客様と漢方相談をするときには目黒区の漢方薬局桂林堂は、中医学を利用してお客様に適切な漢方薬をお出していています、今回この場を借りて中医学の説明をいたします
漢方の本場中国で、2000年以上前にあった漢方を1950年、理論的に便利な中医学を完成
中医学とは 中国伝統医学(Traditional Chinese medicine,TCM)は中国国内で「中医学」と呼ばれ、 中医学は、数千年の歴史がある漢方を、中国古代の陰陽説・五行説に基づき、漢方の治療における実践を経て独自の医学理論システムです
便利な中医学特徴
中医学は現代医学と異なり、独自の理論システムを持っていて、独特な理論システムは大きく二つの特徴があります
「整体観念」と「弁証論治」
整体観念の整体とは統一性と完全性のことを指し、中医学の整体観念は、「人と自然との関連性」二つの内容を持ち合わせています。
人体自身の整体観、統一性を重視し、人は有機的整体で人体を構成する各部分が切り離されることなく、生理的には互いに連携しあい生理活動を維持しており、病理面においても互いに影響しあえる考え方
人は自然界の中で生きている為、気候や季節など自然の変化に影響を受け、人間は社会活動をする中で、環境の変化に影響を受け、それは心身にも影響を与えると考え方
弁証論治は漢方薬局で重要
弁証論治は、(証)=病気や症状・病状を中医学の疾病への認識と治療原則を論じ、
論治は診断法・治療法を示し(「証」を判別・区別してその証に応じた漢方治療を施すこと)このことを弁証論治弁と言います
弁証方法、望診(見る)、聞診(聴く)、問診(漢方相談にて、困っていいる症状を細かく分析)は漢方薬局でしています
切診(脈診・腹診など)の四つの診察法により、患者の情報を集め、一人ひとりの体質や、発病の原因、発病のプロセスを分析し、証を弁別した中医学の診断方法
但し切診(脈診・腹診など)は医療行為になり漢方薬局では出来ません※医師法違反
論治とは、導き出された証に基づき、漢方での治法を決め、漢方、薬膳などを選んで治療を施すことを指します
言い換えるとオーダーメイド漢方医療に当たり、弁証論治は中医学の基本特徴で、中医学の精髄だと言えます。
中医学の歴史傷寒論から
中医学の理論基礎を打ち立て、漢時代(紀元前202-紀元220年)、 張仲景氏ちょうちゅうけいは中医学臨床医学書『 傷寒雑病論 ※3』を編纂しました。
これは最も古い弁証論治 著作であり、のちの弁証論治のシステムを定めました。
補中益気湯・十全大補湯胃腸薬が完成
金元時代(紀元1115-1314年)、色々な流派が誕生し、その中でも日本に多く影響を与えたのは李東垣り とうえん氏、朱丹溪しゅたんけい氏の学説(李朱医学)です
補中益気湯は金元時代の名医である李東垣(杲)(1180年-1251年)により『脾胃論』(1249年)において記された処方
当時の中国は戦乱が続き民衆は飢えと疲労で心身ともに疲弊しきっていた。熱性疾患で多くの人が死亡し、やはり胃腸を立て直す漢方薬が必要と考え、その胃腸疾患を治療する目的で李東垣の師である張潔古の処方に工夫を加え完成したのが当薬であると言い伝えられています
明時代(紀元 1368 年―1644 年)、医薬学者の李時珍り じんちん氏は今までの本草学を全面的にまとめ、のちに非常に有名な『本草綱目』という薬学書を編集しました。
1950 年代以降、中医学の発展と医療レベルを向上させるべく、中国政府は中医学と西洋医学を合わせもつ中西医結合の政策を立てました
中医学と西洋医学の二つの医学システムは、それぞれ長所と短所がありますが、中西医結合はそれぞれの長所を発揮し、お互いに短所を補い合うことを考え作られました。
漢方理論(中医学)は処方選びに最適
また(中医学)は難しい漢方理論を見事に解説していています
A五臓六腑は臓器や臓腑の関係を解説
B三陰三陽は病か体の何処の場所にあるかを解説
C陰陽虚実等は陽と陰の関係を解説
漢方医学に重要な理論を割とわかりやすく解説されています
桂林堂薬局は、この(中医学)を利用した漢方、漢方薬相談を行う漢方専門薬局になります
漢方専門の漢方薬局を開店するにあたって、桂林堂薬局の永山が大学卒業後に3年間学んだ(中医学)が開店に自信を付けてくれたばかりか、実際にお客様に漢方薬をドキドキしながら中医学を学んだおかげで漢方薬を初めてお客様に処方して作ることができました
漢方薬相談 桂林堂の永山は、3年学んだ(中医学)のおかげと便利を実感
東京都目黒区、中目黒地区で、1986年開店当初も、いきなり以前勤めていた三軒茶屋の漢方薬局の元のお客様が多く来店され、やはりそのときも(中医学)を駆使して来店されたお客様にいきなり漢方薬を選ぶことができました

tennaibook_32
中医学でお客様に漢方薬選び
漢方薬の選択は意外にも難しいこと、お客様にどの漢方薬を選ぶのか
どの漢方薬にするのか、または選択するのか悩やんでしまうという漢方専門の薬剤師が多くいらっしゃいます
ところが(中医学)を3年から4年学ぶと意外にもお客様に適切な漢方、漢方薬選択することができます
漢方薬の選択が難しいですが、桂林堂薬局の永山は、これも3年学んだ中医学のおかげで、お客様に効果的な漢方薬を選ぶようになりました
中医学を利用すると、来店されたお客様に適切な漢方薬を悩むこと無く直ぐ選ぶことができます
そのことが東京都目黒区、中目黒で漢方専門 、漢方薬局を40年近くこんなに長く続いたことに驚きます
また、開店日に初めてのお客様がニキビを漢方薬で治して欲しいと来店されました
それも(中医学)のおかげで、赤く化膿したニキビで悩んでいる、中目黒在住の女性のニキビ治療を漢方薬だけで改善しました
赤く化膿ししたニキビは漢方薬 服用2ヶ月で化膿が無くなり、赤みも無くなり、ニキビ顔はキレイになりました
中医学解説続き
A中医学の五臓六腑
五臓六腑は、肝・心・脾・肺・腎の五臓の、各臓器の不調を理論的に解説しています
(肝陽上亢)などがあり、肝うつ病になるとイライラや怒りっぽくなる等の症状と上半身が熱くなり、火照りや発汗の症状が現れます
また、肝うつ病は今の現代人にもかなり多くいます、いつもイライラしたり、怒りっぽくなる方は現代人に多い現象になります
2000年前の漢方医学が2000年後の現代人の症状や現象を予見していることに驚きます
また、(脾)が不調になると、脾虚になり、慢性下痢、疲れやすい、食欲低下等の症状が現れます
腎は成長や髪、かすみ目、冷えなどと関連があり、その腎の働きが低下して腎虚になりと、不妊症、下半身の冷え、抜け毛が増えると言われています
漢方医学では、腎は成長・発育・生殖などと関係し、泌尿器や生殖器と強い関係がありと言われています
また腎臓などの機能を「腎」と呼び、 「腎」の機能が低下したり、不足している状態は「腎虚」と言われています
「腎」は、身体の様々な機能に密接に関わっており、「腎虚」になるといろいろな衰えの症状が現れるようになります
漢方では衰えた状態を「虚」と考えます
漢方薬は2000年前に風邪を主体として発表されましたが、風邪の延長である
咳、喘息、気管支喘息、ちくのう、副鼻腔炎、上咽頭炎などに効く漢方薬は2000年前に早々と出来上がっています
精神的病気や症状に効く漢方薬も2000年前に完成
更に、精神的病気パニック障害、不安障害、適応障害、強迫性障害、躁うつ病、双極性障害などの難しい精神疾患も2000年に漢方薬で改善出来ること
また痛み関係の病気、関節痛、関節リウマチ、筋肉リウマチ、坐骨神経、脊柱管狭窄、腰椎狭窄症、腰痛も2000年前に漢方薬だけで対応出来ることに驚きです
1400年代には胃腸病に効果的漢方薬発表
1400代位になると、体力低下、免疫力低下の国民が中国国内で多く発生しました
やはり胃腸を立て直す漢方薬が必要になり、当時の有名漢方医が胃腸や体力に良い黄耆、人参を見つけ、1400年代は漢方胃腸薬、漢方免疫力強化、漢方代謝改善方法を発表されました
その時代一つ医学である、書万病回春は化膿性ニキビ薬を発表し、その漢方薬は、現代でもニキビに素晴らしい効果を発揮しています
また、体力低下、食欲低下、免疫力低下に効く漢方薬の補中益気湯もこの時代に発表されています
漢方医学の場合、胃腸の働き改善は体の体力や免疫力、食欲低下を改善することになります
胃腸が悪いと人間は何も出来なくなり、体の上中下の中(中)に位置し、やはり、胃腸の(中)を立て直すことが最重要になりました
中医学で漢方、漢方相談
東京都目黒区の漢方薬局桂林堂薬局は中医学を利用し、漢方相談に便利
中医学は統計的、体系的、理論的になっていて、症状や病気で悩んでいる方の病気に対し、理論的に効果的な漢方薬を作ることができます
漢方薬は2000年前に風邪を主体として発表されましたが、風邪の延長である
咳、喘息、気管支喘息、ちくのう、副鼻腔炎、上咽頭炎などに効く漢方薬は2000年前に早々と出来上がっています
(中医学で漢方、漢方相談に便利∣ 桂林堂薬局∣ 東京都 目黒区