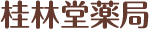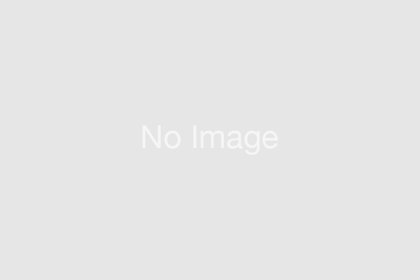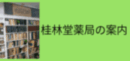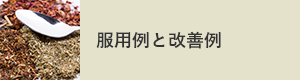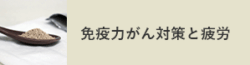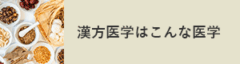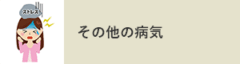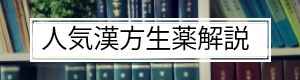解毒体質にならない為に∣東京都 目黒区 ・漢方薬局 桂林堂
解毒体質にならない為に∣東京都 目黒区 ・漢方薬局 桂林堂
一貫堂医学 の分類三大証
解毒症体質になるとの嫌な手汗、困ったニキビ、詰まりが辛い蓄膿まで網羅します決解毒性体質かどうかは決め手は手汗に有り、そんな解毒性体質にならないようにするには日頃の体質改善にあります
一貫堂医学 の分類—-森道伯が晩年に至って完成させた一貫堂医学の特色は、三大証に分類して、単純な五処方の運用法のことになります
またこの体質を3つに分けた分類法は漢方薬処方選びに今現在でも十分通用しています

❶三大証
瘀血が原因で疾病が起こりやすい体質である瘀血証体質、臓毒証体質、解毒性体質
新陳代謝害物などが身体の臓器に蓄積しやすい体質である臓毒証体質、瘀血性体質はほとんどの女性は瘀血性体質と言われています、デスクワークや毎月の生理は瘀血発生源と言われています、今回は三大証の一つ解毒性体質を説明します
➋解毒性体質とは
解毒をはかる必要のある体質である解毒証体質などの分類が特徴です。
森道伯晩年の昭和5年のカルテによると、初診患者の約6割に上記5処方の加減方が用いられており、防風通聖散の加減方が全体の3割以上と特に多く、このほか芎帰調血第一加減、活血散瘀湯、五積散、加味承気湯、清上飲、疏肝湯、柴胡疏肝湯、四物黄連解毒湯、散腫潰堅湯、洗肝明目散などの後世方も一貫堂では良く使用され、柴胡桂枝乾姜湯・大柴胡湯・柴胡桂枝湯・桂枝茯苓丸などの古方の処方も用いられていた。
解毒性体質かどうかは手汗が決め手
解毒症体質は現代人にも当てはまる「解毒証体質」は手汗が決め手ですが、ニキビ、蓄膿まで網羅できますので
❸生まれつき肝臓の解毒作用が弱くいろいろな毒素を解毒排泄できないために、幼少時より発病しやすい体質、特に手汗がある方は解毒性体質と決めつける手立てになります
解毒性体質は結核等感染症になりやすかったが、現在はアトピー性皮膚炎など、アレルギー性体質の人に多い。先天的には丈夫な「臓毒証体質」と対照的な体質で、虚弱で発病しやすく、神経質で手足に汗をかき易い人がターゲットですが、ニキビやアトピー性皮膚炎や鼻の副鼻腔炎にも応用ができます
肝臓の働き(現代医学)
1、胆汁を分泌する
2、体を守る働き解毒作用(解毒作用・排泄作用・生体防御作用)——有害物質(アンモニア、アルコール、化学物質、毒素等)老廃物、(血球、ホルモン等)を代謝無毒化し胆汁に排泄する。・肝臓は免疫に重要な役割を持つ。
3、体に必要な物質の新陳代謝(合成・分解・貯蔵)
糖代謝・蛋白質代謝:消化吸収されたアミノ酸を体に必要な蛋白質に合成し貯蔵し必要な時に供給する。・脂質代謝:消化吸収された脂肪を体に必要な脂肪に合成し、貯蔵し必要な時に供給する。
(コレステロール、中性脂肪等)・ ビタミン・ミネラル等の合成・血液を貯蔵する。・肝臓は非常に大きな臓器であり、血液量も多く、全身の血液の流量を調整している。また赤血球の代謝、血液凝固に重要な働きをしている。
肝の働き(漢方医学)では
肝は将軍の官、謀慮を主どる。(素問:霊蘭秘典論)
肝とは国にたとえるならば国、国民を守る軍隊で、警察、消防、中央政府の一部等までも含み、外敵、災害等に備計画し、また実行する。と有ります。
疏泄作用———-疏泄の疏は順調に通じる意味、泄はすこしずつ漏れでる意味で排泄、発散のことで、肝の疏泄作用がうまくいっていれば気血がスムーズに流れ調和し、精神活動は安定し、五臓のバランスがとれ身体が安定する。
蔵血作用(肝は心がめぐらす、血を貯蔵し血流量を調節する。)——–肝は血を蔵す。(霊枢:本神篇)・人臥するとき、血は肝に帰る。(素問:五臓生成論)
人体各部の血流量には生理的な変動に応じた変化があり、活動時には大量の血を全身各所に分布して需要をみたし、休息時や睡眠時には一部の血を肝臓に貯蔵する。
筋を主る。
目に開竅し、その華は爪にある。
❹解毒症体質の治療には
下記の温清飲加減の三処方を使用・応用で対応します。
解毒用体質改善には、柴胡清肝湯、荊芥連翹湯、竜胆瀉肝湯等の漢方処方を使い
アトピー性皮膚炎やニキビ体質、副鼻腔炎・ちくのう等、現代人に多い慢性病に効果を発揮します。
血虚とは、血のもつ濡養(栄養・滋潤)作用の不足
解毒性体質改善には血虚に効果がある漢方薬当帰、地黄、センキュウが配合されています
血虚とは、血のもつ濡養(栄養・滋潤)作用の不足のことで、原因として、脾胃の運化作用の低下にともなう血の生成の不足、出血や血液破壊による血の量の不足、循環不全(血オ)による血の供給不足が考えられます。
血虚【主症状】
顔色が悪い・皮膚に艶が無い・唇のあれ・爪が脆い・目がかすむ・目が乾く・目がくらむ・ふらつく・動悸・四肢のしびれ感・筋肉がひきつる・筋肉のけいれん・舌質はやや淡白・脈は細。
心血虚(心の「神を主る」「血脈を主る」の機能異常)不眠・夢をよくみる・動悸・不安感・健忘など特徴である。
肝血虚(肝の「血を蔵す」「目に開籔する」「筋を主る」の機能異常)目がかすむ・目の乾燥感・筋のけいれん・手足のしびれ・脈は弦細、女性では月経のおくれ・月経血の過少・無月経などが特徴です。
いずれも、脳の抑制過程の機能低下・自律神経系の失調・心筋や筋肉の代謝異常などによって生ずる症候と考えられます。
【論治】
治法は補血(養血)です。一般に当帰・熟地黄・奇薬・何首烏・阿膠・早蓮草を用い、心血虚には丹参・酸渠仁・柏子仁・遠志・竜眼肉などの養心安神薬を、肝血虚には拘杷子・桑甚子・鶏血藤などの補血養肝薬を加えます。
補血薬は、滋養強壮・栄養・神経機能改善などの作用があり、間接的に造血機能も促進します。ただし、補血薬は味がしつこく消化不良を起こしやすいので、健脾薬を配合するとよいです。
【代表方剤】
●補血剤。
帰脾湯・四物湯・補肝湯・加味帰脾湯・炙甘草湯など。
●補血薬。
当帰・熟地黄・何首烏・白芍薬・阿膠・竜眼肉。
解毒症体質の漢方薬/ 東京都目黒区の漢方薬局 桂林堂薬局